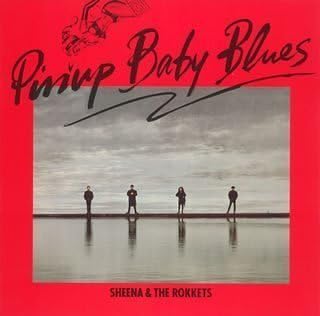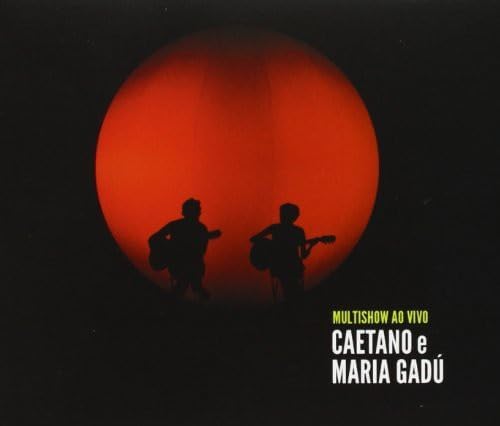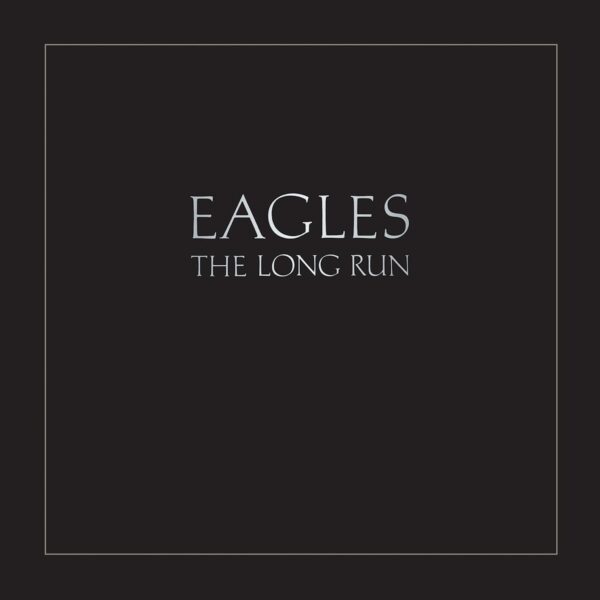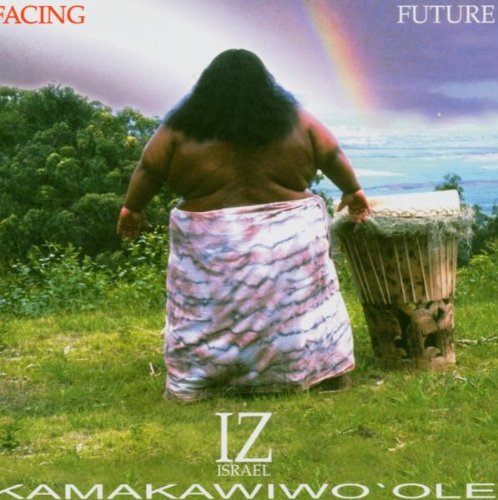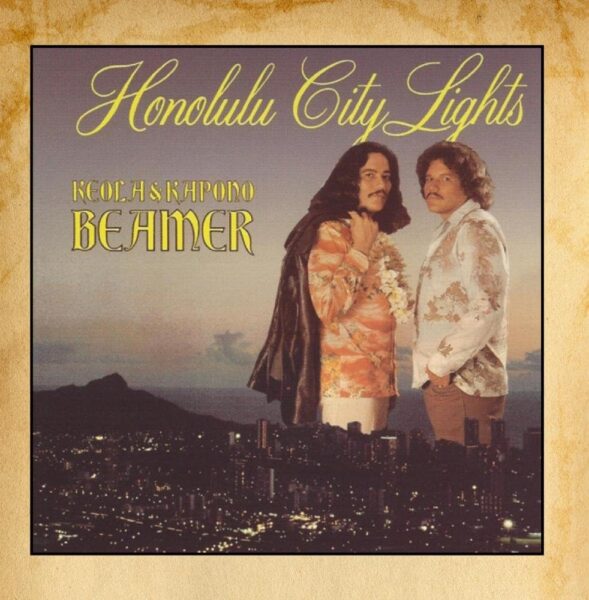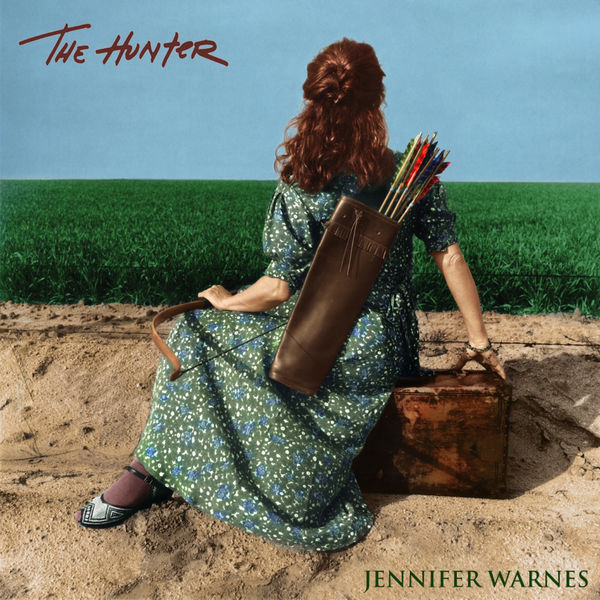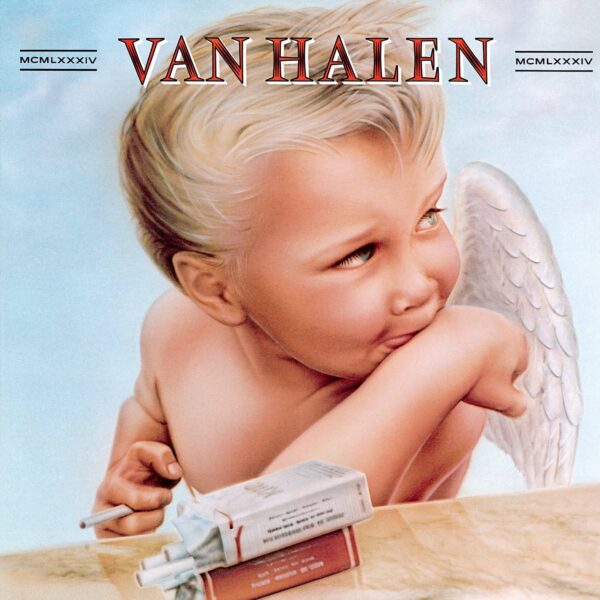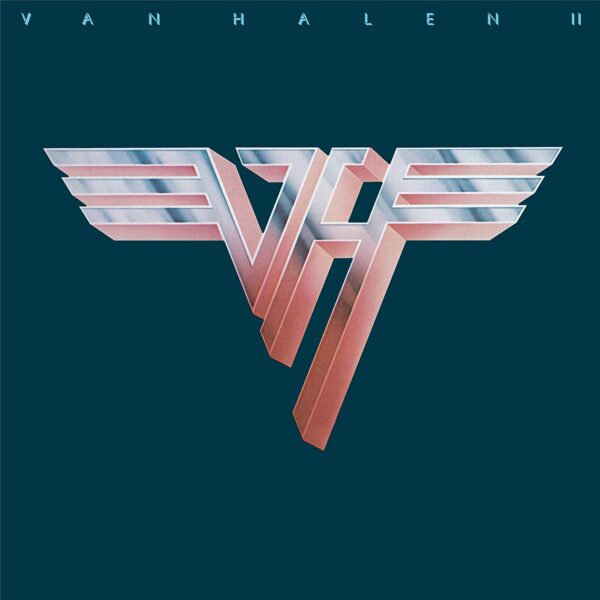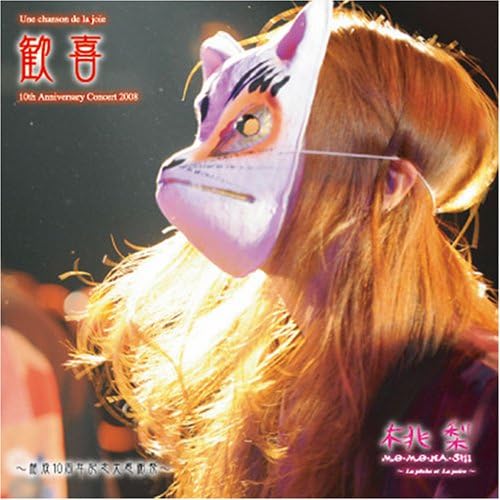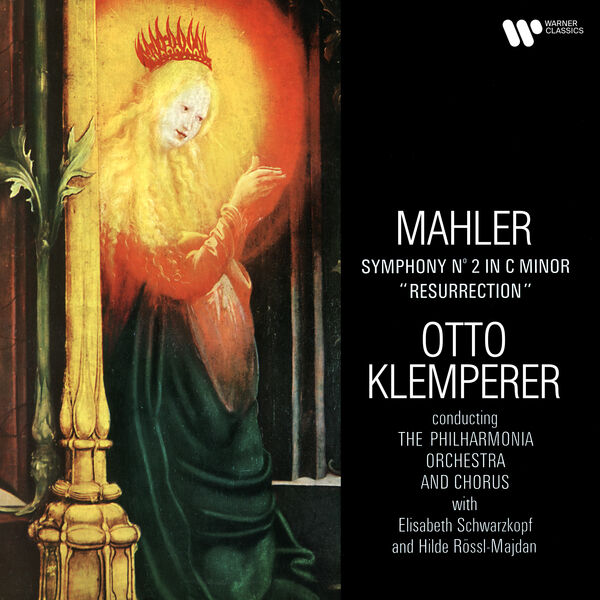暑中お見舞い申し上げます。連日暑いですね。エモーション代表の橋本です。
毎年、「このところの暑さは異常です」などと言う言葉が、既に耳タコになるほど聴こえすぎる酷い暑さが続いておりますが、今回は、オーディオの話題から少しそれて、夏に合う音楽をご紹介したいと思います。
私が思春期を迎えた70年代終わりごろ、そして青春期の大半を過ごした80年代、青年期だった90年代、それらの年代を通じて、夏は活動的な、一年で最も楽しい時期であり、朝から晩まで、夜通しでも遊びまわるのが当たり前と思われていた時代でした。音楽もそれを助長するかのような明るく楽しい音楽や、夏の恋を歌ったセンチメンタルな曲、過ぎゆく夏を惜しむ惜別の曲。そんな音楽にあふれていました。
しかしどうでしょう、それから時代が下って2010年代以降のこの猛暑。昼間に海辺で寝そべっているなどと言う行為はもはや自殺行為とも呼べそうなほどの過酷な暑さの夏、とても青春や恋などと言った言葉を発する元気も出ないほどぐったりしそうですよね。
そこで今回は、酷暑で少し鬱屈した気分も含めた、夏に聴きたい音楽をご紹介しようと思います。宜しくお願いします。
ただし音楽が90年代以前に偏っているのはご勘弁を。その理由の一つには私が古い人間であるということ、もう一つは夏を楽しく彩る曲は意外と古い時代の音楽に多いということが挙げられます。お若い読者の方々は、新たな発見としてお読みください。同年代の方々は、再発見と言う視点でお読みいただけると幸いです。
○ ピンナッピ・ベイビー・ブルース / シーナ&ロケッツ
81年録音、プロデューサーはミッキー・カーティス。
孤独感を抱えた青年が、地下鉄の車内に貼られた夏らしいポスターの女性を好きになるという心象描写的な歌詞で、やや屈折した青春を描いています。現代にも十分通用する、反逆的なロックスピリッツが隠された名曲です。
この曲が良いと言える点は、この時代の作としては十分良い録音なのですが、オーディオ的な高音質と言うよりも、唯一無二の音の質感を持ち、聴く者をその世界に引き込んでいくといった点でしょうか。
その秘密はコンサートホールを使った”一発録り”にあります。
一発録りはスタジオやホールで録音されますが、コンサートホールやライブハウスが用いられる方が多いようです。ただし録音時にホールやハウスには観客は入れませんのでライブ録音ではありません。ライブではありませんが各パートを個別に録音しミキシングする手法ではなく、ライブと同じようにバンドがステージで演奏し、それを一発で録音するという、演奏者にとっては非常に緊張感を要求する方法で録音されます。
これは、「シーナ&ロケッツの音楽には一発録りが似合っている」と言う、ミッキー・カーティスのアイデアから始まっているそうです。ギター、ベース、ドラム、ボーカルと言う、シンプルな編成だったシーナ&ロケッツに、伝説のサックス奏者、スティーブ・ダグラスや、ピアニストのノジケンこと野島健太郎を迎え入れているのもミッキーさんのアイデアなのだそうです。
音楽ホールでの一発録りでしか表せられない、独特の響きや艶が聞き取れ、それがまた、孤独な夏を歌ったこの曲のイメージに奇妙にマッチしています。
Qobuzからハイレゾ音源がDL出来ます。
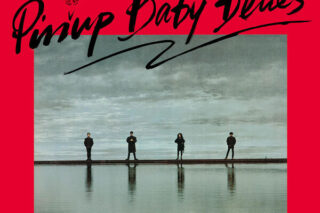
○ TREM DAS ONZE / Caetano Veloso , Maria Gadu
TREM DAS ONZE(トレム・ダス・オンゼ)ブラジルサンバの大変有名な曲です。オリジナルは1964年のアドニラン・バルボーザによる作曲と歌唱で、それと同時にデモニオス・ダ・ガロアと言うグループによって大ヒット、その後多くのアーティストにカバーされ続け、ブラジルでは現在に至るまで年代を問わず愛される曲です。 邦題は「11時の夜汽車」。
貧しい女性が恋人と朝まで一緒にいられない。家族が眠らずに待っているから、家の手伝いをしなければならないので11時の夜汽車で帰らなければならない。と言うことを歌っています。
様々なバージョンがありますが、音楽的にもオーディオ的にも、最もお勧めなのはカエターノ・ヴェローソとマリア・ガドゥとのデュエットによる2010年録音のライブバージョンです。
お聴きになられてお気づきだと思いますが、一般的に日本人がイメージするリズミカルでパーカッシブなサンバではなく、深く陰鬱なバラードです。こういう形態のサンバをサンバ・カンサオンと言い、1920年代から70年代まで非常に盛んに歌われた形式でしたが、その後1950年代に登場したボサノバに吸収されるような形で縮小しています。しかし音源とヒット曲の数は膨大で、このTREM DAS ONZEのように、老若男女問わず歌い続けられる名盤となっている曲も少なくありません。
ハイレゾ版は今のところ存在しませんが、CD版やDL版でもかなり高音質で、何よりも暑く物悲しいブラジルの夏の夜と言う雰囲気をしっとりと、艶やかに感じ取ることが出来ます。
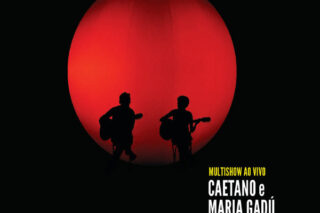
ついでなので、この曲の他のアーティストのバージョンも動画で紹介しておきます。
音源を入手したい場合はブラジル輸入雑貨店の通販などでCDも買えますよ。
MANU & GABRIELによるバージョン、残念ながら現在音源入手は極めて困難。
ブラジリアンサンバのグループ samboによるバージョン、日本人がイメージするサンバに最も近いかな。
ブラジルのGAL COSTAによる1973年のバージョン、時代的にフレンチポップスの影響を感じますね。明らかにボサノバ化されています。
○ THE SAD CAFE / EAGLES
私は誰もが知る音楽をわざわざ紹介することを好みません。しかし超が付くほど有名なアメリカンロックバンド、イーグルスの最後のアルバムである、THE LONG RUNの最終トラックに入れられた、決して有名とは言えないTHE SAD CAFE(サッド・カフェ)と言う曲は、知る人ぞ知る隠れた名曲だろうと思います。故に、ここで取り上げる価値を感じました。
サッドカフェはシングルカットされておらず、数あるイーグルスのベスト盤に入っていることもあれば入っていないこともあり、人気面ではイーグルスの楽曲の中ではセカンド、サードポジション位に位置していると思われます。
話は変わりますが、日本では、70年代から90年代にかけて「喫茶店文化」と呼べるようなものがありました。
ネットもSNSもない時代、喫茶店は出会いの場であり、仲間との交流の場であり、語らいの場であり、高校生や大学生などの青春の場でした。多くの喫茶店に落書き帳が置いてあり、スマホの無い時代の良い伝言板となっていたほか、面白い投稿は新聞の夕刊にも取り上げられるなどと言ったこともあり、結構必死になって書いている人もいましたね。
そこで語られる内容は、身近な遊びの事や、恋愛、他人のうわさ、将来への漠然とした不安、中には社会を変えられるとか世界を変えてやるとか、思いっきり背伸びした会話が大真面目でなされることもありました。
そしてそのうち皆大人になり、現実に目覚め、家族が出来れば喫茶店などで長居することなどしなくなり(寂しくなくなるのでその必要がなくなる)、昔喫茶店の中で大言壮語を並べたことを恥ずかしく思うようになり、それと同時に、そんな時代に郷愁を感じるようにもなります。
っと、まぁこんな風に、70年代~90年代に青春を送った日本人がいるわけですが、サッド・カフェで歌われている内容は、こんな喫茶店文化に少しだけ似ています。
意外ですよね。アメリカでも似たような喫茶店文化があったのでしょうか。あったのかもしれませんが、イーグルスはそこに別の意味を込めたのではないかと考えます。
イーグルスはこの曲の中で、「昔日の、仲間たちとの、サッドカフェでの思い出は、主の恵みに守られた聖地みたいだった」と言うような事を歌っています。そして「愛や自由と言った言葉と共に、世界を変えられると思っていた」自分たちを恥じるかのように歌っています。
これは、イーグルスが自分たちのバンド活動を、サッドカフェの中で起こる喧騒にたとえ、それをを良い思い出として称えながらも自嘲気味に語り、解散するバンドの最後のアルバムの、最後の一曲に込めたのではないかとも取れます。
デビッド・サンボーンのサックスが哀愁たっぷりにこの曲の最後を飾り、そしてフェイドアウトしていきます。
この曲をもって、イーグルスはバンド活動にピリオドを打ちたかったのかもしれませんね。
雰囲気としては、残暑厳しい晩夏の夕方、海岸線を車で走りながら楽しかった夏を思い出し、そしてかつて最も輝いていた時代の夏を邂逅する。そんな気分にさせてくれる曲です。
この曲は、2025年7月現在、CD版もハイレゾ版も2013年リマスターが最新です。もしかすると、そろそろ新たなリマスターが発売されるかもしれませんね。
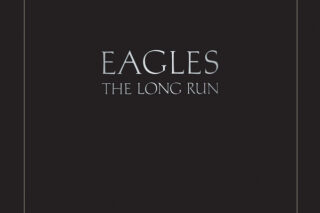
○ Kuhio Bay / Izrael Kamakaeiwo’ole(イズラエル・カマカヴィヴォオレ)
なんとまぁ、読みにくい、覚えにくい名前なんでしょう。イズラエル・カマカヴィヴォオレ、一般的にはIZ(イズ)と愛称で呼ばれていますので、ここでもIZで通します。
伝説のハワイアンシンガーで、ハワイアンの神とも称される人物。1959年に生まれ、1997年に37歳という若さで肥満により死去。その崇高なる肥満は死の直前には340kgを超えていたとも言われています。
葬儀の日には、ハワイ州の州旗が半旗掲揚となり、1万人以上が集まったとされています。
IZのアルバムの中では、曲、音質共に、このFacing Futureと言うアルバムがお勧めで、捨て曲なしの名曲ぞろいです。
その中から、Kuhio Bayという曲をピックアップします。
2000年代ごろ、米国のカーオーディオイベントに行くと、このアルバムをデモに用いるメーカーやショップが少なくありませんでした。しかし日本では完全に知る人ぞ知る存在でしかなく、ハワイが好きだと言う人でも知らない人がいるくらいでしたね。おかしいですね。IZはハワイアンの神と言われているのに。その方は本当にハワイが好きだったのでしょうか。
湿度の高い日本の夏でも、雨上がりで見通しがよくなった晴れの日には、こんな曲が聴きたくなりますね。
現在、輸入盤CDのみで入手可能です。もしかしたらどこかのDLかストリーミングにあるとは思いますが、私は探しきれませんでした。
○ Honolulu City Lights / Keola Beamer
次は、同じハワイアンでもハワイアンポップスの名曲、ホノルル・シティ・ライツです。
ハワイアン独特のギター奏法である、スラック・キー・ギターの名手、ケオラ・ビーマーによって、1970年に録音されました。
ケオラ・ビーマーと言うと、カリフォルニアのサーフィンを舞台にした青春映画「ビッグ・ウエンズデー」のエンディング曲、Only Good Timesでも有名です。
ホノルル・シティ・ライツは、旅行者がハワイを去る前日、ホノルルの夜景を眺めて”ハワイ去り難し”と感傷に浸る内容の曲です。
作曲者ケオラ・ビーマーのバージョンがこちら。
残念ながら、現在、中古CDしか入手方法はありませんが、ストリーミングにはちらほらとあるようです。
音質面で言えば、カーペンターズのバージョンが良いと思います。
音符の小節の位置を少し変えるだけで、随分カーペンターズっぽくなりますよね。
ハイレゾ版はありませんが、CD版やDL版でも良い音です。
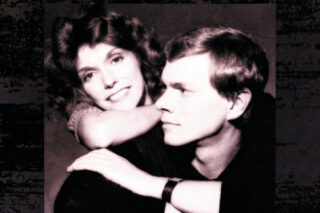
杉山清貴もカバーしていました。
イントロに波音のSEが入りエンディングに飛行機音のSEが入るところがいいですね。このバージョンを聴いていると、”ハワイ去り難し”と言う思いがひしひしと伝わります。2016年のリマスターが優秀で、驚くほど音質改善しています。CDは絶版でDLで入手可能です。ストリーミングにもあります。
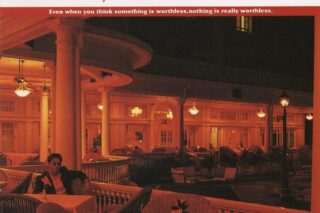
面白いところでは、香港人女性ボーカルの、Shirly Kwan(シャーリー・カーン)のバージョンが結構優秀だと思います。
この人は1989年から1990年まで日本で活躍していた人で、その時に発表したアルバムにホノルル・シティ・ライツが入っていました。しかしヒットには至らず撤退。香港に戻ると大人気歌手となり、今でも活躍しています。
シャーリー・カーンのバージョンは、車メーカーのマツダがフォードとタイアップしていた時代に、マツダ製のフォードブランドを売るオートラマと言うディーラーを展開しており、そこの人気車種フォード フェスティバのCMに起用されていました。1990年の録音。
大変良いバージョンだと思うのですが、残念ながら、現在CDは絶版、DLではベスト盤で入手可能です。ストリーミングだと結構存在しています。
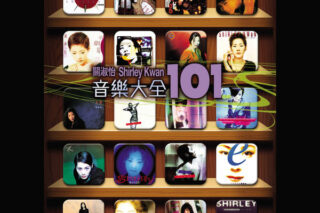
○ Lights of Louisianne / Jennifer Warnes
オーディオの世界では定番中の定番と言われる名録音で、1992年の録音ながら音質は抜群。いまだにオーディオ試聴会などで使われることの多い高音質録音です。
私はこのアルバムの中でも、よくオーディオデモに使われる、Somewhere,Somebodyや、Way down Deepなどよりも、ルイジアナの夏の夜をテーマにしたLights of Louisianneが好きですね。
AIによると、Lights of Louisianneとは、とは、ルイジアナの民間伝承によく見られる、火の玉現象(feu follet、またはfifolletとも呼ばれる)を指していると考えられます。これは、特に湿地や沼地の上空で夜間に見られる、雰囲気のある幽霊のような光、あるいは不思議な光です。ルイジアナでは、これらはしばしば悪意のある、あるいは悪意のある霊と結び付けられ、旅人を死に誘い込むと言われることもあります。
だそうです。
真夏の夜の夢のような、ファンタジック歌詞が特徴の曲です。
ジェニファー・ウオーンズ以外にも数人カバーしていますが、どれもあまりよいとは感じず、今のところこの曲に関してはジェニファー・ウオーンズのバージョン一択ですね。
ハイレゾ版、CD版、DL版と、音源は揃っています。

○ JAUMP / VAN HALEN DANCE THE NIGHT AWAY / VAN HALEN
ハードロック系、文章によってはヘヴィメタル系と言う記載もあるヴァン・ヘイレンから二曲をご紹介します。
アルバム1984に挿入されているJUMPは大ヒット曲、私が紹介するまでもないでしょう。
VAN HALEN Ⅱに入っている、 DANCE THE NIGHT AWAYはとにかく明るく、夏にぴったりで、ヴァン・ヘイレンの隠れた名曲と言っても良いでしょう。
JUMP
DANCE THE NIGHT AWAY
ハードロック界屈指のスーパーギタリストである、エドワード・ヴァンヘイレンのギターは、心地よい歪み感と透明感があり、つぶ立ちが良くリズミカルだと感じます。
ジャーニーのニール・ショーンや、TOTOのスティーブ・ルカサーのように軽快で、典型的なヘビメタギターであるブラックサバスのトニー・アイオミのように重く、イングウエイ・マルムスティーンのようにリフが多彩です。つまりあらゆるハードロックギターの要素をエディがギタープレイに取り入れている感じがします。と言うよりも、他のギタリストがエディの要素を取り入れていると言った方が良いのかもしれません。多分両方でしょうけど。
まぁ私個人の印象ですので、聴こえ方は皆さん様々でしょうけど、エドワード・ヴァンヘイレンの音は、ヘビメタにしては非常に綺麗な音だと思います。
ヴァン・ヘイレンの音源は、古い時代のロックでありながら大変優秀だと思います。透明感やリバーブ感に満ちていて、音場がしっかりと感じられる録音が多いのも特徴です。
また、ベースやドラムスの音も特徴的で、ギターほど表に出ませんが、低音よりも中低音から中音に存在感を持たせ、裏でプレイしていても輪郭がしっかりと聞き取れるように録音されています。これがギターの音をより綺麗に聞こえさせているのではないでしょうかね。
是非、ハイレゾ版で楽しんでみられてください。


ヴァンヘイレンのハイレゾ版には二種類あり、ただ単にHiResと書かれたものと、カッコつきで(Remastered)と追加されたものがあります。
必ずハイレゾ版の(Remastered)と追記されているものを買ってください。これは2015年版のリマスターで、過去のリマスターの中では私が最も良い音だと思うものです。
〇 桃梨
アルバムによって「モモナシ」とカタカナ表記であったり、momonashiとアルファベット表記であったり、「桃梨」と漢字表記であったりするので検索しにくいのですが、どれも同じバンドです。
弦を一弦分高くしたテナーベースを用いる超絶テクのベーシストJIGENと、独特の声質を持つボーカルの上村美保子により、1998年に結成された音楽ユニットです。
テナーベースと言うのは、一般的なベース弦であるE-A-D-Gの最も低い音の弦であるE弦を外し、最高音弦であるG弦よりも上のCを加え、A-D-G-Cにして演奏するベースのことを言うそうです。一般的なベースと比べて1弦分音が高いということですね。
これにより何が良くなるのかと言うと、和音が美しくなるのだそうです。なるほどJIGENさんが解説している動画では、高い弦(C弦)が追加されただけで、和音が非常に美しく聞こえてきました。これにより、ベースがボーカルの伴奏に、より適した楽器となるのだろうなと推察できます。
この桃梨、楽曲を通じて夏っぽい音楽が多いことから、特定の曲ではなく、音楽ユニットとして取り上げました。
特に夏とが関係なさそうな歌詞とメロディですが、アコースティックテナーベースと上村美保子の特徴的な声が、なんとなく夏を連想させます。お盆休みに実家に帰省した夜、しっとりと聞きたい感じがします。
この「月と昴」を含むアルバム、「贅沢な時間」は、現在CDはモモナシ公式サイトでのみ入手可能のようで、moraからDL販売されているほか、各種ストリーミング再生が可能のようです。
ツキノアカリは夏を少し過ぎたころ、中秋の名月ごろに楽しみたいですね。
ベスト盤に収録されています。
目下最新のアルバムである”最高の続き”(2020年)に収録されている「思い出の散歩道」は、ノスタルジックな曲で昭和中期の歌謡曲をモチーフにしていることは間違いないでしょう。音作りもアナログ風に、響きやリバーブ感を抑え、レンジを敢えて狭くすることでレコードプレイの質感を出していると思います。モモナシの音源の中で唯一ハイレゾ配信されています。
また、モモナシの楽曲全般、モモナシ公式サイトからも購入可能です。
随分たくさん、しかもくどく解説してまいりました。文章量が多く読みにくかったら、動画リンクだけでも楽しんでいただければ幸いです。
書いているうちに「あれも、あ、あれもいいかも」と次々に楽曲が浮かんできましたが、それはまた次の機会に。
懲りてなければまた付き合ってください。
お読みただき、ありがとうございました。
エモーション 橋本